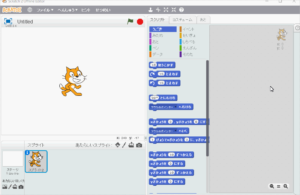新しい内閣が生まれ、
携帯料金引き下げなど嬉しい話が出てくる中、
「デジタル庁」設立という話がよく取り上げられています。
昨日も承認のハンコを廃止する話が出ていましたね。
でも「デジタル庁」って、
行政機関のデジタル化を進めるところだろう、
と、なんとなくイメージできるのですが、
なんでこんなに大騒ぎするのか、
と思われる方も見えると思います。
今まで紙とハンコでうまくいっていたのに
なぜわざわざ電子化しなければならないのでしょうか。
その変更に伴う労力に見合う効果が得られるのでしょうか。
今回の「デジタル庁」は、
行政機関を対象とするものですが、
実は民間企業でも深刻な問題です。
なのでここでは、
企業も含めた組織のデジタル化
についてお話ししたいと思います。
この四半世紀、中国をはじめとする新興国が力をつけ、
経済発展を遂げてきました。
私、実は1990年代に中国に何か月か滞在していたのですが、
当時、彼らの主な通信手段は「BP機」と呼ばれる
ポケベルでした。
若い人は知らないかもしれませんが、
ポケットに入れられる受信機で
どこからか電話をすると、その電話番号が表示され
受けた人が近くの公衆電話から連絡を取る、
というものです。
日本にもポケベルはありましたが、
まだ固定電話全盛の時代です。
日本では各家庭に固定電話が普及していましたが
中国には電話網が少なかったため
BP機が利用されていました。
その後、携帯電話が発展し、
世界中の人々が、固定電話網を使わずに
電話をすることができるようになりました。
日本で普及するよりもずっと早いスピードで
中国では携帯電話が普及したのです。
それも現在はスマホとなり、中国では
屋台の支払いもQRコード決済となっている映像が
ニュースで流れていました。
日本よりデジタル化が進んでいますね。
固定電話網を設置するには
莫大なコストがかかります。
中国などの新興国はそれをスキップして
効率よく通信ができる国となったわけです。
電話に限らず、新しい技術によって
効率よく経済発展した例はいくらでもあります。
日本でも、江戸時代の鎖国によって
世界から取り残されてしまった技術レベルを取り戻すため
明治時代から海外技術を積極的に取り入れてきました。
自ら研究開発するのではなく
欧米の技術を導入するだけなので、
回り道も少なく
効率よく進化できたのだと思います。
そのおかげもあり、20世紀後半の高度成長を迎え
世界トップクラスの生活を送れるようになりました。
ただ、あまりにもうまく成功してしまったため
その成功例から外れた行動がしにくくなりました。
既存の知識を身につけさせることを重視する
受験勉強も、昔の成功体験を引きずったものと言えます。
会社でも、事業収益が上がらなくなってくると
改善しなければなりませんが、それでも
「昔はこうやって成功・成長したんだ」、
という体験が、
新しいものを導入する妨げになっている
かもしれません。
考え方が変わらない限り、
その組織のシステムも変わりません。
今までこれでうまくいっていたんだから、
という雰囲気は、簡単に押し返せるものではありません。
そんな中で、新興国は
この10年、20年で生まれてきた新しい技術を
次々と導入して、効率よく成果を上げてきています。
日本でも同じですが、新しく生まれた会社や組織は
既存のシステムがないため、
最新技術を取り入れたシステムに
自分たちの業務を合わせることができます。
業務効率が良くなれば、
同じサービスを安く提供することができます。
社員の給料に還元することもできます。
逆に従来のシステムで業務を続けることは、
自分たちの所得を下げてしまう結果に
繋がりかねません。
今のうちの会社のシステム、無駄が多いよな、
この労力で、どれだけ損失がでているんだろう、
と思われた方も見えるのではないでしょうか。
日本の企業、特に大企業は
何十年も続いているため
巨大なシステムを持っており
新技術を取り入れるためには
膨大なコストを要します。
最初から最新技術に合わせた仕事でビジネスができる
新しい会社と比べると、不利な戦いですね。
巨大隕石ほどではないですが、
新技術という隕石によって
徐々にビジネス気候が変動していく中、
恐竜のように環境の変化に対応できず
絶滅していく企業も出てくることは、
想像に難くありません。
普通に生活していると
そんな雰囲気は感じられませんが、
海外の情勢を肌で感じている人たちは
このような日本の状況に危機感を持ち
警鐘を鳴らしてきました。
特に日本企業では、
その業務を管理する基幹システムが
何十年も引き継がれており
クラウドなどの新技術を取り入れることが
困難な状態となっています。
システムの老朽化も進み、
そのメーカーも開発を終了しているため
ここ数年で動かなくなってしまう
基幹システムが大量に発生してしまうのでは、
という懸念があり、
経済産業省ではこれを
「2025年の崖」と呼びました。
しかし現実の企業や組織は、
なかなか変わることができません。
やはり変わることに対するコストが
(実務担当者の負担も含め)
重くのしかかっているのだと思います。
このような背景から、
今回の「デジタル庁」の話となったのだと思います。
行政機関でうまくいったら、
民間企業にも転用しよう
という考えじゃなかろうか、
と個人的には推測しています。
問題は基幹システムだけではありません。
社内で大量の紙がやり取りされています。
情報が部署間、下手をすると担当者間で
やり取りされる度に
新しい紙(帳票)が印刷され、
そこに記入するたびに
転記チェック作業が発生します。
そして何か所かで押印する必要があります。
使い終わった書類は、倉庫に運び込まれ
数年間、所在が不明にならないよう
管理しなければなりません。。。
紙とハンコで仕事をすることで、
どれだけの時間が、
本来の利益を生む出すために費やすべき時間を
奪ってしまっているのでしょうか。
社外とのやり取りも未だファックスが多く、
いくらスキャナで電子化しても
その情報は単なる画像情報であり、
本当の意味での電子データに落とし込むために
文字読み取り、そのエラー・チェックなど
無駄な時間が浪費されていきます。
これらの作業は、1円の利益も生み出しません。
例えば受発注などの社外とのやり取りなら
EDIやWebサービス化すれば、ほとんど
人手が要らなくなると思います。
(共通フォーマットの問題等ありますが。)
物理的な紙もハンコも使わずに
業務を回せる技術は、すでにあります。
切り替える手間、コストが問題となっています。
日本では
「おもてなし文化」「顧客第一主義」のせいか
製品、サービスは、顧客に合わせるもの、
というイメージが、海外に比べて強いと感じます。
そのため新しいシステムの導入には
膨大なカスタマイズが必要となり、
中小企業サイズのシステムでも
億の単位のお金が必要になってきます。
海外に比べ、日本の企業は
システム開発を丸投げする傾向が強い
と言われます。
海外の企業ではシステム開発する人員を確保し
常にシステムを進化させていくのに対し、
日本の企業がシステム部員に求めるのは
現状維持で、
トラブル時に迅速に復旧させることが最優先、
というところが多いのではないでしょうか。
ERPという便利な管理ツールも、
海外ではそれをベースに
システム人員が開発したものを社内で活用する一方、
日本では、そのままでは自社の業務体制に合わない、
でも改造を外注すると億の単位を請求される、
という理由で採用されなかったケースが多いようです。
そして、このような改革は、
企業の資本に余裕があるからこそできます。
このまま引き延ばし続け、
新興企業との競争力の差が決定的となり
切羽詰まって資金繰りに悩む状態で、
さらに短期的に経費が増える改革は
できません。
コロナ禍で厳しい状況ではありますが、
会社に少しでも余裕があるのであれば
やらなければ先はないと感じます。
デジタル化における大きな課題の一つは、
新しいシステム、仕組みを導入するためには
従来の業務を変えなければならない、
そのことに対する経営者、社員の拒絶反応です。
日本では教育時に理系・文系が明確に区別され
受験でも偏った知識で通ってしまうため
(社会現象に関心の薄い技術者や)
科学技術に興味のない経営陣、社員が多く存在します。
おそらく食わず嫌いも相当数いると思われるので、
日ごろからIT等の最新技術に触れて
使い方に慣れていく機会が増えていけば
いずれ社内から自然に
デジタル化の声が上がっていくのではないか
と思っています。
業務がラクになるのなら導入したい、
って、誰でも思いますよね。
ただし、AIでも、RPAでも、IoTでも、
それさえ入れれば、全てがうまくいく、
という夢の道具とは、なり得ていません。
いくら優れた道具があっても、
それを使いこなすことができなければ、
その道具はなんの役にも立ちません。
人から仕事を奪うな、という意見もあります。
もちろん雇用を守るのは、大事なことです。
しかし、全ての会社が従来のやり方をしていれば
バランスは崩れませんが、
新興国などが効率の良い業務システムで仕事をすれば
価格競争力に差が出るのは当然のことです。
日本中の企業が現状維持を続けていても、
結局、日本全体のビジネス基盤が沈降し、
多くの人達の賃金が低下していく
のではないでしょうか。
機械導入によって人減らしをする、のではなく、
自動化できる部分は機械に任せ、
人は機械に出来ない仕事をしていかなければ
そのビジネスで食べていけなくなります。
出来ることは限られていますが、
老若男女問わず最新技術を使いこなす、
そんな世界の実現を、「Dr.+エジソン」は目指しています。